![]()
新制大学が発足すると、何れの大学も旧制大学に追いつこうと懸命の努力をした。
徳島大学学芸学部(当時)数学教室では工学部の数学教室の諸先生と合同して談話会や輪講会を初めた。
当時は耐乏生活の時代で 自由に他大学へ出かけて共に研究討論する機会をもつ事が少なかった。
その時、阪大の清水辰次郎教授発行の全国紙上数学談話会にならい、田村孝行氏が中心となり渡辺義勝教授と相談 の上、四国数学紙上談話を徳島大学学芸学部数学教室より発行した。
応募論文は日毎に増して応募者も全国的になって隆盛になった時、会費の収集が思わしくなくついに廃刊の止むなきに到った。
残念なことではあったが数年に及ぶ刊行は僻地四国における数学の研究発達に貢献するところ大であったと言わねばならない。
四国数学紙上談話雑誌もおいおいと散逸して今は私の所有するもののみとなった。之を永久に教育学部数学教室にとゝ゛め、建学当時の苦労の一端を後世に伝えたい。
昭和57年3月 霜田 伊佐衛
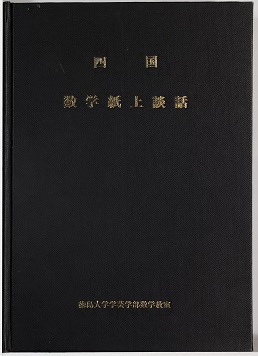

「四国数学紙上談話」は、昭和26年〈1951年)6月発行の第1号から昭和31年〈1956年)5月発行の第27号までの5年の間、全国の数学研究者および教育者が投稿した徳島大学学芸学部数学教室主催発行の和雑誌である。現在は、徳島大学学芸学部教授であった霜田伊佐衛氏が、昭和57年に製本した2分冊が、数学教室に残されている。しかし電子化した資料を見て頂ければ分かるように、ガリ版刷りでインクが経年劣化しつつあり、元々劣悪であった紙の酸化も激しい。このまま放置しては、早晩貴重な資料が二度と読めなくなることが危惧されていた。
この度、総合科学部数理科学教室が、この貴重な資料を後世に残すために電子化して、広く公開することとなった。一読していただければ、敗戦後の日本に於いて、四国の一地方新制大学が、数学を研究する自由な場を全国に呼びかけて提供し維持し続けた努力の跡が分かっていただけるに違いない。
なおこの電子化の成功のためには、下記の方々の協力が不可欠であったことをここに申し添えておきます。
まず、劣化の激しい資料を丁寧に電子化する作業をしていただいた光楽堂出版(京都市)に感謝いたします。
また徳島大学総合科学部に残されていた上記の2冊子では、欠けていた第20号を含めて、個人で所有されていた「四国紙上談話」全資料を教室に寄付していただいた阿南工業高専の名誉数学教授の福島光男氏に深く感謝いたします。
最後に「四国数学紙上談話」の発足に携わり、「四国数学紙上談話」を冊子として我々に託していただいた故霜田伊佐衛氏に深く感謝いたします。
2014年 5月 総合科学部数理科学教室 片山 真一
このサイトでは、昭和26年から昭和31年にかけて、徳島大学総合科学部数理科学教室の前身である学芸学部数学教室主催により刊行された「四国数学紙上談話」を電子化した資料(PDFファイル)を公開しております。自由に閲覧ダウンロード可能ですが、ファイルを引用される場合は、下記の教室のURLを明記くださるようお願いいたします。 http://www-math.st.tokushima-u.ac.jp/ この度、「四国数学紙上談話会」を html 化してあらたに公開することにしました。 このような形での公開に不都合がございましたらご連絡下さい 。 |